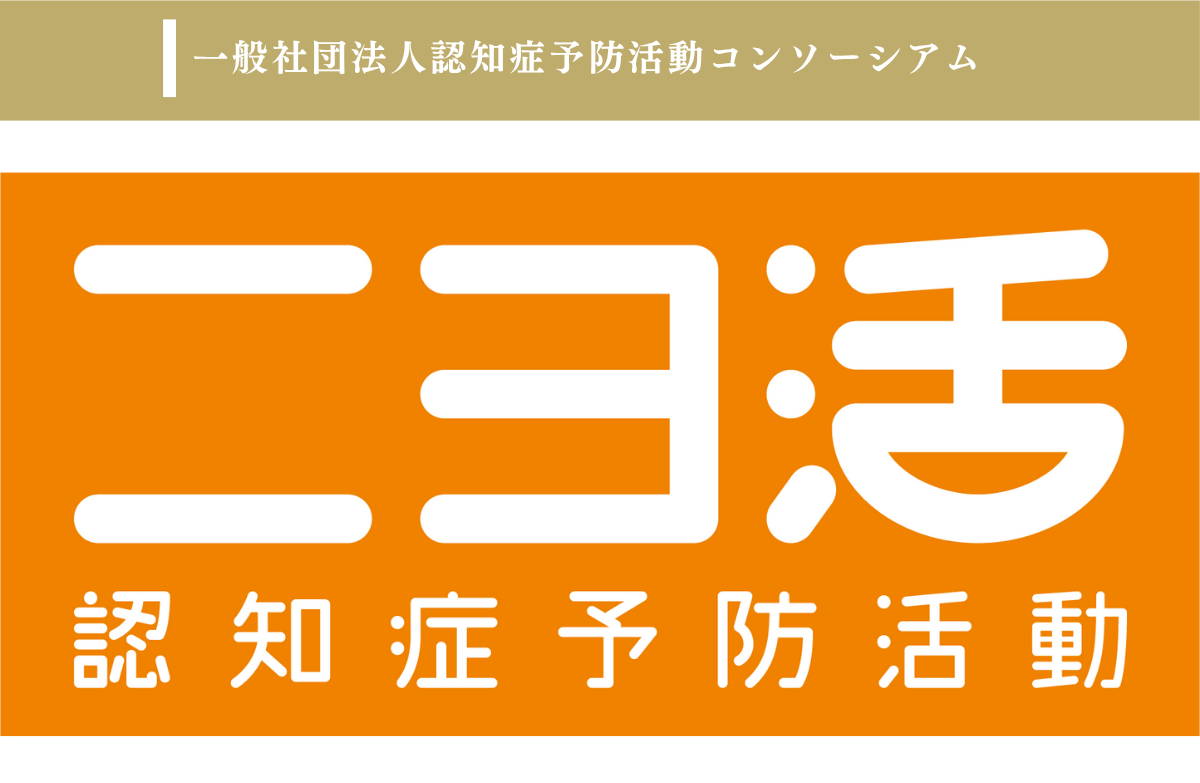事業内容・活動内容
「認知症で人生をあきらめる人をゼロに」
「認知症で人生をあきらめる人をゼロに」を理念に、認知症(二)予防(ヨ)活動(活)を行っています。家族や自分が認知症になってからではなく、若い世代が早くから「認知症と生き方」を考えていただくきっかけの活動です。認知症をテーマにしたイベント企画・運営、高齢者の生きがいの場、通いの場作り、若年性認知症当事者の夢叶えるプロジェクト、予防の為の健康講座・健康体操の提供などを行っています。
イベントは「ニヨ活フェス」と称し、認知症をテーマにしながら、来場者は「楽しかった!」という感想を持ってお帰り頂ける内容です。企画の段階から、ニヨ活が事前に調べた、魅力的な地域活動団体や、事業者に多数声をかけ、その活動の発表の場として使っていただき、盛り上げていきます。そこで生まれた各団体・各事業者の出会いが新たな地域活動の連携になるように、その後も交流の場を作ったり、必要に応じておつなぎして、その活動の支援をしています。他にも「オレンジリンピック」と称し、健常者だけのオリンピックでもなく、障がい者のためのパラリンピックだけでもなく、そもそもバリアのない、みんなが対等に競い合い笑い合える概念のスポーツ大会を開催しています。また認知症をテーマに研究をされている先生方と一緒に「認知症シンポジウム」も開催しています。
常時活動としては、認知症の症状緩和に期待できる「なごみマフ」の推進、ミニらいとモルックを使った多世代スポーツ交流の場の提供、脳トレ体操教室、今さら聞けないスマホ教室、アロマハンドケア教室、認知症予防講座の提供を行っています。
苦労していること・苦労してきたこと
認知症というと、介護や福祉の問題と受け止める方も多く、一般の方には興味がないといわれやすい状況です。
またニヨ活は予防だけ、社会共生だけ、ではなく両輪を回していくための活動なので、大切な活動だけど一緒にやりづらいと行政にいわれてきました。なぜなら予防は健康保険の分野になり、共生は福祉の分野になるため制度が異なるからです。
また大阪の場合、介護事業や福祉事業など収益事業は区役所轄の福祉課が担当で、ボランティア活動は社会福祉協議会が担当となるなど、管轄が全く異なるため、情報も区切られ、ニヨ活のような幅広い活動はたくさんの実績の積み上げがないと、行政との連携が難しいと感じています。
しかし、たくさんの方に知っていただくためには、行政との連携は大切と考えています。そこでスタート時より、変わらず実績の積み上げに邁進していますが、活動は資金調達が必要で、ボランティア助成金をとるか、企業に協賛を頼むか、それでも足りない場合は自己資金によって続けています。
活動実績
2018年9月18~21日の4日間空堀通商店街で認知症予防啓発イベントを開催/来場者1000名以上→「ニヨ活」という言葉が生まれた。
2018年~毎(月)午後「ニヨ活」として、地域の高齢者の通いの場を作り、運動、脳トレ、講座、アロマハンドなどを提供/来場者常に20弱程度
2019年2月4日大阪市立天王寺区民センター「ニヨ活フェス」開催、認知症サポーター養成講座、ステージショー、体験などを提供/来場者200名弱
2019年6月若年性認知症の元カメラマンの写真展「おおさかの空」をあべのハルカス近鉄本店で開催/来場者50名程度
2019年8月認知症当事者と一緒に舞台に立ち、予防と共生の想いを伝える「合唱団ニヨカンタービレ」結成/団員30名程度
2019年9月大阪市立鶴橋小学校体育館で「ニヨ活フェス2019秋」開催、認知症当事者と対等に競い合うスポーツ大会/来場者250名程度
2020年2月大阪市立天王寺区民センター「ニヨ活フェス2020冬」開催、予防の講座、討論会、ステージショー、体験などを提供/来場者300名弱
2020年9月コロナ禍にて「ニヨ活フェス24hオンライン」開催、24時間テレビのようにzoom、YouTubeを駆使してライブ配信
2021年~2月と9月にはあべのハルカス近鉄本店で「ニヨ活フェス」を開催/来場者常に500弱程度
2022年12月、2023年2月、9月ミニらいとモルックをつかった「オレンジリンピック」(認知症当事者を含むユニバーサルスポーツ大会)を開催
2023年3月、兵庫県伊丹市でニヨ活フェス、奈良県天理市でコフフンカップ(天理市向けオレンジリンピック)、近鉄本店で縁活カップ(縁活事務局主催のオレンジリンピック)を開催。/来場者常に150名程度
2023年9月「口腔ケアからはじめる認知症シンポジウム」を国際交流センターで開催/来場者50名弱
2024年2月「腸内環境からはじめる認知症予防シンポジウム」をエルおおさかで開催/来場者130名弱
2024年6月「子どもたちの未来に活かす認知症シンポジウム」を大阪大学SSIと共催にて、大阪大学中之島センターで開催予定/リアル100名・オンライン100名
事業・活動を始められた経緯と解決したい社会課題
日本は医療・福祉・介護が充実した国の一つですが、介護が必要となる期間が平均9年もある、世界一介護期間の長い国です。認知症をテーマにしているのは、高齢者が一番かかりたくない病NO.1であり、医療だけでは対応が難しい病であり、介護も人生観を変えてしまうくらい、人としての成長につながる病だと思っているからです。
また現実的に日本は2025年にはMCI(軽度認知症)を含むと1300万人になるという数字に危機感を持っています。
認知症の罹患率は他国に比べ高い上、日本はさらに少子化が進んでいます。
今も大変な高齢者介護ですが、この先、私たち世代が介護と必要となる時の未来はもっと大きな社会問題になっていると考え、2018年(ほとんどの製薬会社が認知症の根治薬の開発を撤退した年)この活動をスタートしました。
今の高齢者に「認知症予防」をすすめることに重きをおくのではなく、親の介護が始まるかもしれない働く世代を含む多世代に発信しているのが特徴です。
親の介護の準備のためにも認知症のことを知っておくべきですが、それよりも認知症は、医療・介護・福祉がなんとかしてくれる問題ではないことを知っていただきたいと思っています。それを知ることで自分たちで社会をどう作っておくべきが一緒に考える人を増やしたいのです。その先の自分たちの未来を支えてくれる今の子どもたちの未来は、今私たち世代が何をするかで変わるからです。
将来の展望・目標・VISION・志
他人事とせずに認知症をきちんとしって自分はどうしたいのか?を考えていくことで、医療任せにしない健康意識が高まり、医療費・介護費の削減も期待できます。
また認知症は介護施設に入るのは重度になってからがほとんどで、それまでの中軽度の期間は誰かの手をかりて社会を生きていくことになります。つまりは認知症は、介護や福祉に関係のない一般の方たちの理解がないと、社会生活していくことが難しくなります。たくさんの方ができるだけ早くからどのような手があれば必要なのかと考えていくことで、相互社会の必要性が浸透し、認知症になっても安心して生きていける共生社会が実現できると考えています。それは介護費用の削減にもなります。
2023年認知症基本法が制定され、共生社会とは何か?というテーマはこの先もっと深堀されて行きます。その中でこれまでのニヨ活の人脈やノウハウが活きると考えています。「認知症シンポジウム」で学び、「オレンジリンピック」で共生を体感し、「ニヨ活フェス」を地域活性化のために行うなど、お役に立てる場所を全国に広げていきます。
今の共生社会の考え方は認知症の方との差をなくすバリアフリーに重きを置いているものが多いように思います。ニヨ活ではバリアフリーではなく、ユニバーサル社会共生の実現を目指して、「豊かな人生と優しい社会をつくる」活動を推進しています。
団体情報
団体名:一般社団法人認知症予防活動コンソーシアム
住所:大阪市天王寺区東高津町5-17新聞印刷本社ビル4階
代表者名:歌丸 和見
メールアドレス:mail@niyokatsu.com
サイトURL:https://niyokatsu.com/
SNSアカウント①:https://www.facebook.com/niyokatsu
SNSアカウント②:https://www.instagram.com/niyokatsu/